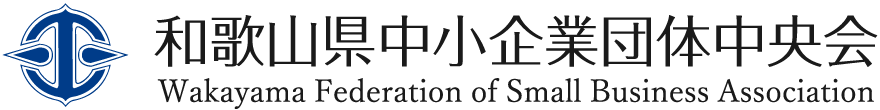景況調査
【2025年10月分】前年同月比の景気動向
増加・好転 不変 減少・悪化
| 業種 | 売上高 | 収益状況 | 資金繰り | 業界景況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 食料品 | ||||
| 繊維工業 | |||||
| 木材・木製品 | |||||
| 印刷 | |||||
| 化学・ゴム | |||||
| 窯業・土石製品 | |||||
| 鉄鋼・金属 | |||||
| その他 | |||||
| 非製造業 | 卸売業 | ||||
| 小売業 | |||||
| 商店街 | |||||
| サービス業 | |||||
| 建設業 | |||||
| 運輸業 | |||||
| DI値 | -32.5 | -55.0 | -15.0 | -55.0 | |
(情報連絡員40名のうち回答数40名 回答率100%)
製造業
食料品
農林水省大臣が代わり、国の米政策の朝令暮改と思える変更は消費者のみならず食品産業に携わる者にとっても、不安視せざるを得ない。(食料品製造業)
梅干し原材料価格は高止まりで、かつ原材料不足が深刻な状況での年末商戦の不透明感は否めない。(食料品製造業)
繊維工業
原材料費の高騰や最低賃金引き上げの影響で苦慮している企業が多い。また、学生服などの取り扱い企業は、販売価格上昇でも少子化が進み販売減で収益状況悪化との声もあった。(繊維工業)
昨年同時期と同様の状況。産地内の加工場や染工場も稼働に関しては昨年と同じような状況である。(繊維工業)
売上は前年同月と比べて増加した。今年は夏場の高温期が長く、秋がないと言われていたが、11月から秋を越えて冬期に入るとの予測があり、秋冬物の受注が増えた。組合員からは近年検品、ミシン加工、セット加工、梱包などの手作業が高齢化や人手不足により思うように進められないとの声が出ている。特に内職作業員は、時代の変化や一般の労働時間給のアップなどで極端に減少している。(繊維工業)
木材・木製品
依然、住宅の売れ行きは悪く苦戦している。今年は特に4号特例(※)の見直しに係る建築確認の遅れが特殊な悪い影響を及ぼしている感触があり、慢性的に住宅需要が振るわない。また、人口減少による住宅購入層の縮小だけでなく、日本経済の好調さに反して持ち家を必要とする年代の夫婦の収入が向上していないのも大きな要因である。こういった状況の中で、プレカット構造材の製造業は、購買業者の値切りや他のプレカット製造業者との競合が厳しさを増している。注文を取れないことが起こっており、収益の低下に拍車がかかっている。勝つためには価格競争のみの一択となっていると言っても過言でない。この先良くなるといった見通しを持てない業況となりつつある。(木材・木製品製造業(家具を除く))
価格転嫁等がうまくいっておらず、低空飛行が続いている。(木材・木製品製造業(家具を除く))
組合員の動向は経営者及び作業従事者の年齢が高齢化し、後継者の育成も不景気を背景として良くない状態である。業界を取り巻く問題点としては住宅着工数の減少及び工期の遅延化が際立ってきている。地域の実情としては、当地域は受注だけに頼る特徴があり、低迷状態である。(家具・装備品製造業)
製材業の受注量・プレカットの生産加工量・ 原木市場の単価について、すべて前年同月比で横ばいであった。(家具・装備品製造業)
本年は、年末納品の物件が多く、現在図面承認待ちとなっている状態である。大阪駅周辺の再開発で、今後も内装工事が断続的に出てくる見込みだが、和歌山県下は、住宅工事、店舗工事ともにあまり動きがない。(家具・装備品製造業)
印刷
相変わらず印刷原材料価格の高騰は続き、そのうえ11月からの人件費の上昇で、ますます収益状況は悪化すると考えられる。価格転嫁が早々必要となるが、人件費に対しての値上げは実現しがたいと一部の組合員からの意見があった。また、人材に対して、人材採用イベントに参加したが会社見学の申込等1名もなかったとの話もあった。(印刷・同関連業)
化学・ゴム
トランプ関税の影響がどんなものなのか、はっきりしない。物価は継続的に上昇しており、これが収益の減につながっていく。少数与党ということが経済や景気にどういう影響を与えるのか注視している。(化学工業)
窯業・土石製品
昨年同月は比較的出荷数量があったため前年比としては約3割減少した。全国的に出荷量は減少傾向にあり、歯止めがない状態となっている。この傾向は10年以上前から続いているが、ここ5年は顕著になっている。持ち直しは期待できず商品の付加価値を模索して価格を上昇させようという試みが全国である。(セメント・同製品製造業)
鉄鋼・金属
前年同月比で売上高は、約3%増加した。価格転嫁は、満額とは行かないが要求の半分ほどはできている。しかし、人材の確保にはまだ問題が残っている。(金属製品製造業)
長年の技術と職人力を持つ一方で、設備更新や人材確保の遅れが課題となっている中小企業が多く、後継者不足や人手不足が深刻である。今後は、技能継承・デジタル化・高付加価値化を進めることで、持続的な成長に期待したい。(金属製品製造業)
現在の組合員の各企業は、経営状況に特段の変化はないが、今後、取り巻く環境は厳しくなっていくように思われる。賃金引き上げを行うために、価格転嫁に取り組んでいるが、すぐに成果をあげるのがむずかしい。今後の鉄鋼業界の動向を注視しているところである。(金属製品製造業)
その他の製造業
経済状況は厳しい状態のまま変化はなく、先行きが見えない状態が続いている。(なめし皮・同製品・毛皮製造業)
業界全体の売上が下落している状況で、原材料価格の高騰・後継者不足も加速している。価格転嫁、賃金引き上げをせざるを得ないと思うが、なかなか難しい課題である。(その他の製造業)
原材料価格の高騰を踏まえ、値上げの安否を迅速かつ的確に判断できるように社内システムの構築にも注力している状態である。(その他の製造業)
現年の対前月比売上高はやや減少している。相変わらず為替の影響で、売上が上がっても収益が上がらなかった。物価高騰により、家庭用品等買い控えの傾向が続いている。(その他の製造業)
非製造業
卸売業
土物野菜の入荷量の減少と価格高騰が顕著になってきている。(飲食料品卸売業)
業界の県内の人手不足は深刻で、県外流出が年間約3,000人で15歳から24歳までの若年層が約8割である。また、県外進学率が80%以上であり、進学先の不足や就職機会の乏しさ、給与水準、キャリア形成、ライフスタイルの多様性などを求める都市部への志向も要因とされる。当組合においても若手の人材確保が難しい状況である。取扱商品については値上げが来年から順次行われる予定である。インフラの老朽化による更新需要も増加しており、主要材料における電線価格については中期的には上昇傾向と予測される。電線需要は再生可能エネルギー・データセンター・EV・送電網強化などで底堅いようである。(機械器具卸売業)
小売業
原材料費の高騰により、収益が少し下がっている。(飲食料品小売業)
ガソリン税と軽油引取税の旧暫定税率廃止の移行措置として燃料油価格対策の補助金が段階的に増額される。現在、石油の元売などに㍑当たり10円を支給している補助を10月13日から2週間ごとに5円ずつ増やすことになった。ガソリンは、12月31日に税率廃止となる。軽油は来年4月1日に税率を廃止する。SS現場では補助拡充による価格の引き下げは、消費者の一定程度の買い控えや引き下げ後の反動なども想定されるため制度の周知、工法の徹底を求めている。(その他の小売業)
素材やエネルギー価格の高騰と円安によって輸入時計や宝飾品はもちろんのこと国内生産の品物も価格上昇を続けています。需要増加での価格上昇ではない為、売上が付いていっていない。(その他の小売業)
商店街
業況は厳しく、利益確保が出来ていない状況である。(複合業種(和歌山市))
今月の天候は悪くはなかったが、先月までの猛暑の影響が続いているので、来客数が戻らない。(複合業種(和歌山市))
サービス業
ガスの売上は微増、ガス仕入は円安ではあるが、輸入価格が下落傾向のため収益は若干好転している状況である。(ガス業)
売上は対前年比は店舗別に86%~124%で、各施設によってバラツキがある。インバウンドについては高野山、熊野古道、勝浦等は特に賑わっており、和歌山市ではたま駅長を目当てに貴志川線の乗車がよく見られる。しかしながら人手不足は相変わらずで外国人技能実習生の採用が多く、国はベトナム、インドネシア、ミャンマー、ネパールが主となっている。(宿泊業)
10月の対前年同月比の宿泊人員は102.9%、総売上高97.8%、1人当り消費単価95.1%、総宿泊料金107.0%、1人当宿泊単価104.0%だった。2025年1月から10月の宿泊人員は、836,734人で、前年同期間(2024年1月から10月)と比べると42,292人の増加である。(白浜温泉旅館協同組合)
10月の売り上げ及び客数は、一部の業種を除き、コロナ禍以前を超えている店舗もみられるが、厳しい店舗も多くみられる。居酒屋では、個人客はまずまずであるが、家族での飲食は減ってきている。物価高騰が続く中、節約は外食の削減からと考える家庭が多いのではないかと予想される。依然として、厳しい状況には変わりがない。スナック等の夜の営業は、企業による接待の利用が少なく、厳しい状況が続いている。温泉・観光地の飲食店やホテルはインバウンドによる外国人等により賑わっているが、パンダショックにより、昨年度と比べると売り上げが減少している。また、10月13日で最終日を迎えた大阪・関西万博による来客者を大いに期待していたが、残念ながら、ほとんど影響が無かった。その他には、依然として、原材料費、水道光熱費等の高騰が続いており、経営状況は苦境に立たされている。それに加え、今年の最低賃金の65円引き上げ決定で、小規模の飲食業者の経営がさらに大きく圧迫されることが予想される。(飲食店)
物価上昇に伴い価格改定する機会が増え、取引先に申し訳なく思う。配送料、郵便料金の値上げ等により取引先への負担も大きくなっている。(自動車整備業)
消耗品や交換部品の原価高騰などで経費が増大し収益性を圧迫している。人口減なども相まって業界の状況は厳しい状況が続いている。(自動車整備業)
材料費等の高騰が続く中、売上は低迷し、資金繰りは悪化している。(自動車車体整備業)
建設業
令和7年10月の県工事受注額については、今まで少なかった分が出てきて少し増えたが、累計では前年度と比べると1割強の減であり、厳しい状況が続いている。(総合工事業)
公共工事受注状況は、国、県、市町村全体で激減している。昨年同時期の受注高との比較ではほぼ同等の水準だが、労務費・材料費の高騰を考慮すると、実質10%~20%の減の実情である。(総合工事業)
全体的に建設業界は厳しい状況が続いている。資材価格の高騰が続いており住宅着工数が伸び悩んでいるので、個人向け住宅需要は減少傾向にあるが、反対に公共工事は持ち直しているようである。また、スーパーの物価上昇や自動車販売台数も前年割れしており、建築需要にも波及されるように思う。住宅着工数が増加しない限り厳しい状況が続くと思われる。(職別工事業(設備工事業を除く))
業況は不変か悪化の声が多く、小規模業者ほど売上は減少しているようである。また年度末に向けて後継者がなく廃業することによる脱退希望者の声もでている。(設備工事業)
運輸業
景気の冷え込みなのか荷動きが悪い。様々なコストが上昇する中で、売上げが下がり資金繰りが厳しい。(道路貨物運送業)
地域内での景況感があまり良くない。ミカンの出荷も本格化するなかで、これから稼働率があがり景況感も良くなってきてほしい。軽油の価格については、相変わらず高値で推移している。(道路貨物運送業)